チャネルを超えて体験をつくる。大手アパレル企業が語る、店舗とアプリで相乗効果を生み出す方法
「APP DIVE」は、プレイドが主催する顧客視点の施策およびプロダクト改善に主眼を置いた企業横断的に学び合う場です。第4回では、「アパレル業界のしくじりから学ぶユーザー視点のプロダクト改善」をテーマに、株式会社ライトオン、株式会社ストライプインターナショナル、株式会社アーバンリサーチの3社にご登壇いただき、しくじりから学んだ店舗との協力体制の築き方や顧客の声との向き合い方などをお話しいただきました。
「APP DIVE」は、プレイドが主催する顧客視点の施策およびプロダクト改善に主眼を置いた企業横断的に学び合う場です。第4回が2021年4月7日にオンラインで開催されました。「アパレル業界のしくじりから学ぶユーザー視点のプロダクト改善」をテーマに、株式会社ライトオン、株式会社ストライプインターナショナル、株式会社アーバンリサーチの3社が登壇しました。
誰に、何を届けるために、どのようにアプリをグロースしていくのか。目先の数字にとらわれるあまり、時に見落としがちな顧客との向き合い方・顧客視点に立ち返る重要性が語られました。
リリース後すぐに停滞したアプリDL数。回復のきっかけはチャネルの「役割の見直し」
はじめに登壇したのは、株式会社ライトオンのオムニチャネル部ECチームの平良綾子氏です。同社は、ジーンズを中心にとしたカジュアル衣料を販売する小売企業。全国に約420店舗を展開しています。
公式アプリをリリースしたのは、2016年3月のこと。2021年3月までの5年で累計340万ダウンロードを達成するなど、多くのユーザーに活用されています。ただ、この数字は順調に伸びてきたわけではありませんでした。
平良氏「リリース直後こそ、紙のカードに貯めていたポイントをアプリに統合させてECサイトでも使えるようにするなど、利便性に惹かれて多くのお客様がダウンロードしてくださいました。しかし、すぐにダウンロード数もアクティブユーザー数も伸び悩んでしまったんです」
伸び悩みの引き金となったのが、アプリのリリース後に始めたLINEの公式アカウントの配信。ユーザーとの接点が二分化したうえ、アプリとLINEの役割が不明確に。 ユーザーもアプリを使うメリットを実感しにくく、徐々に離れてしまったのです。危機感が募ってはいたものの、強みである全国の実店舗を巻き込んだ促進の取り組みも、満足にできない状態が続きます。
そのような時に、新型コロナウイルスが流行。外出自粛によって実店舗への来店者数が減り、店舗の売り上げが減少してしまいます。この状況を打破するために、注目されたのがアプリでした。直接顔を合わせることが難しい中、「ユーザーとの重要な接点」として見直され始めたのです。
平良氏「コロナをきっかけに、アプリが提供できる価値とは何かを考え抜きました。アプリで実店舗のような接客を実現できるのではないか、私たちの強みである実店舗とアプリが融合したような体験を届けていきたいと考えたんです。アプリにOMOツールとしての役割を託すことにしました 」
同社は、アプリのリニューアルを決行。「より探しやすく、使いやすいデザイン」「ユーザーのエンゲージメントを高めるスタンプカード」「手元の商品詳細を補完するQRコードリーダー」の3つのアプローチを取りました。
平良氏「店舗に入ると、性別やアイテムなど、自分が欲しいグッズのジャンルが分けて置かれていますよね。それを、アプリ上でも再現できないかと考えて、性別ごとにホーム画面を設けるなど、お客様が自分に合った商品を選びやすくしました。
また、『アプリの起動』『店舗への来店』『商品の購入』のタイミングでスタンプを付与する仕組みにしました。アプリを開く楽しみを増やし、起動率を高めることで、ブランドとの結びつきを強めたいと考えています。
さらに、実店舗の商品の札に記載されているQRコードをアプリで読み込むと、在庫状況やオススメのスタイリングを見られるようになっています。わざわざ店舗スタッフに聞かなくても、お客様が好きなタイミングで知りたい情報を得られます」
加えて、実店舗を持っているという強みを活かすため、同社は店舗スタッフの力を借り、アプリの活用を促していきました。
平良氏「お客様と最前線で接するのは店舗のスタッフです。顧客体験を最前線で作り上げる彼らの協力なしにはアプリの普及はないと考え、スタッフとのミーティングを開きアプリのミッションを説き続けていきました 」
その結果、店舗でアプリを新規ダウンロードしたお客様に「500円OFFクーポン」を配布することに。店舗スタッフも積極的に協力しやすい形となり、リニューアル後の1カ月間で20万ダウンロードを突破。iOSストア内「無料ファッションアプリ」のランキングでは9位に入るなど、ダウンロード数を伸ばすことができました。

平良氏「ダウンロード数が伸び悩むというしくじりで学んだのは、アプリの役割を明確にし、お客様と接する店舗スタッフと共通認識を持つことの大切さです。
そして、店舗スタッフとはさらに綿密にコミュニケーションを取りたいとも感じています。今回のリニューアルを振り返ると、最初の頃はスタッフへの説明といっても資料を見せただけでした。その後、デモアプリをリリースし実際に使ってもらったところで改善要望が多く集まり、改修に時間がかかってしまいました。
OMOツールとしてお客様に良い体験を届けるには、店舗スタッフとの連携は欠かせないということを強く実感しましたね」
目先の数字にとらわれていないか?顧客に届けたい価値を問い続ける
2人目に登壇したのは、株式会社ストライプインターナショナル DX部の伊藤大揮氏です。同社は、「earth music&ecology」を始めとしたアパレル事業や飲食事業などを展開。伊藤氏が所属するDX部は、ファッション通販サイト「STRIPE CLUB」や、その公式アプリの運営を支援しています。

今回、伊藤氏がテーマに挙げたのが「サービス改善においてのしくじり」です。
伊藤氏「私たちは、サービス改善を『お客様に、より満足していただくための取り組み』と定義しています。ただ、サービスを改善する手段の選定と、評価は非常に難しいですよね。私たちも非常に苦戦しました」
サービス改善をするうえで、DX部とEC事業部で結成されたプロジェクトチームは、ポップアップを活用したキャンペーンの告知などをする「販促」、お客様の会員ランクに合わせた割引などの「UX」、新機能のお知らせなどの「お客様への提案」の3つの側面からお客様へのアプローチを開始します。いずれの施策も数値としては一定の成果が出たものの、「顧客体験」という点においては、価値を提供できたのか疑問が残ると話します。
伊藤氏「ポップアップでお知らせしたキャンペーンの売り上げが上がったり、UXを改善した結果、CVRが1.5倍に増えたりと、『指標』で判断すれば大きな成果を上げたと言える施策もありました。しかし、いずれも長期的に捉えるとお客様の体験を損ねた可能性があるかもしれないと感じたんです。
例えば、サービス全体を俯瞰したら、告知したキャンペーンだけに売り上げが集中しただけだったり、普段通りにアプリを利用したいお客様の体験を損ねてしまったり、そういう可能性があります。
告知ひとつにしても、お客様のためになる情報ではなく、サービスの提供者側が押し進めたい内容になってしまうことがあると思います。私たちは、目先の指標を向上させることが本当に顧客体験の向上につながるのかを、常に問い続けています 」
伊藤氏は、印象的な事例として、2020年に「STRIPE CLUB」に実装したライブコマース機能を紹介。「スタッフがライブ配信で紹介した商品をそのまま購入できる」という機能で、リリース後はアプリ内での告知に力を入れたものの、思うような成果が見られませんでした。
伊藤氏「この結果から、『工数対効果に見合わないのではないか』『いや、結果を急ぐにはまだ早い』とチーム内でも意見が割れました。どちらの言い分もわかるのですが、当時の私たちは平行線の議論ばかりが続き、だんだんとメンバーの士気が下がってしまいましたね……」
ライブコマース機能をやめるべきか、あきらめずに続けていくべきか。瀬戸際に立たされた同社が選んだのは、「続ける」選択でした。
伊藤氏「最終的には『お客様に届けたい体験がある以上、あきらめる必要はない』と判断しました。もともと、ライブコマース機能は、『スタッフとのやりとりを通して、目の前の商品を購入できるリアルタイム性や、店舗でコミュニケーションをとっているような温かみを体験してほしい』という思いから始めたもの。確かに工数に対して費用が見合わないという声はありましたが、目的を見直した結果、短期的な「指標」だけで判断するのは意味がなく、中長期的に見てお客様に届けたい体験を重視しました 」
この経験を通して、チームに浸透したのは、「指標に捉われすぎることなく、前向きな仮説を持って挑戦する」というスタンスでした。
伊藤氏「そもそもアパレルは、流行り廃りのサイクルがとても早い業界です。変化を柔軟に捉えて『まずはやってみよう』というスタンスも重要です。
そのスタンスを維持するために、短期だけでなく、中長期での評価軸を持つことにしました。 何か行動を起こす際は、一気にリソースをかけて大きな成果を得たいと考えてしまうのですが、成果が出るまでに時間がかかるものもある。短期の指標だけに捉われない環境を整えることで、メンバーの心理的安全性が上がり、様々なアイデアも生まれるはずです。それが、お客様にとって価値のある体験につながると考えています 」
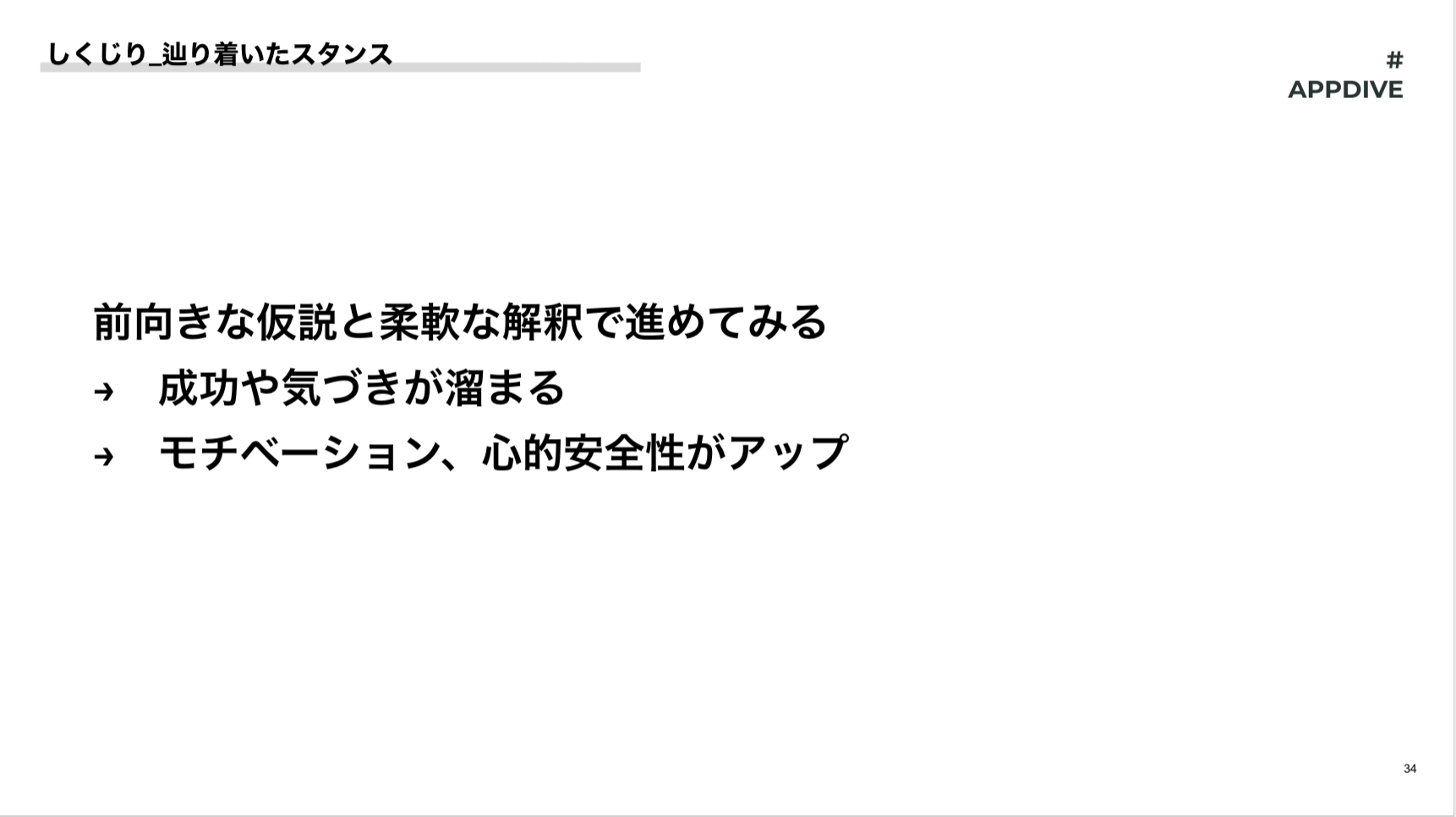
ユーザーの反応を知るうえで、指標となる「数字」は、確かに重要です。しかし、それは何のための指標なのか。正しい評価指標があって初めて、顧客体験の向上にチャレンジできることを学んだ例だったと振り返ります。
自らが「徹底的にユーザーになる」ことで、アプリのユーザビリティを向上
3人目に登壇したのは、株式会社アーバンリサーチのデジタル営業部デザイン課の尻江高昭氏です。同社は、衣類や小物などを販売するセレクトショップを展開。2006年からはオンラインストアを運営し、デジタル化にも力を入れてきました。尻江氏のチームでは、オンラインストアやスタッフによるスタイリング提案、メディアコンテンツなどを配信するアプリの運営を行っています。

多くの機能を持ったアプリを運営する中で、同社が学んだことは、自らが「徹底してユーザーになる」ことの大切さ。 以前は、アプリのさまざまな機能のデザインが統一されておらず、時には情報の重複が見られるなど、「お客様が愛着を感じにくい」アプリだったと言います。
尻江氏「実は当初、デザインのガイドラインなどは存在しないまま、各々がWebサイトやアプリ制作を進めている状態でした。統一化されたフォーマットが存在しなかったため、発注先のベンダーや、制作時期の違いによって、機能面でのカラーに違いが生じていたんです。
ユーザビリティが高いもっと利用されるアプリを目指し、顧客目線で『サービス全体の統一感』に取り組んでいきました。 ガイドラインを策定し、アプリ全体のデザインを整えました。結果的に目的だったクオリティの担保にもつながったうえ、制作からリリースまでのスピードも格段に上がりましたね。 」
徹底したユーザー目線で改善を進めた尻江氏がポイントに挙げたのが「ユーザーと同じデバイスでサービスを体験すること」です。この作業が漏れ、不具合への対応が遅れてしまったことがあったそうです。
尻江氏「パソコンのステージング環境で異常がなかったのに、スマートフォンで起動すると問題が発生することがありました。スマートフォンで利用されることが多いアプリであれば、必ずスマートフォンで確認する。ユーザーと同じように自社のサービスを使いこむ習慣があれば、こうした不具合にも気づけます。ここは盲点になりがちですが、周りのメンバーも巻き込んで、ユーザーになってもらうことを心がけています」
合わせて、同社ではKARTEを活用し、CX調査を実施。NPSのスコアやユーザーのコメントを検証しながら、サービスの改善を続けています。
尻江氏「お客様からのご意見はもちろん、アプリを接客ツールとして使ってもらえるように、店舗のスタッフの声も聞いて、使い勝手やUIの改善を進めています。私たちが叶えたい世界と、ユーザービリティの交点はどこなのか。シームレスな体験をお届けできるように試行錯誤しているところですね」
自分自身がユーザーとして、自社プロダクトの顧客体験を味わってみるという、ユーザーとしての「感覚」を大切にしたからこそ、顧客体験を磨くヒントを多く得られることをしくじりから得られました。
店舗スタッフとの協力体制を築くには?
イベント後半では、3社によるパネルディスカッションが行われ、ライトオン オムニチャネル部ECリーダー 大野一郎氏、ストライプインターナショナル デジタルトランスフォーメーション部部長 榎本一樹氏、アーバンリサーチ デジタル営業部 CRM課マネージャー 清水樹二也氏が登壇。パネルディスカッションでは、アパレル3社がどのように強みである店舗と協力体制を築いているかについても伺いました。
3社とも、全社的な施策として、店舗別のアプリダウンロード数に応じた評価設計でモチベーションを生んでいると話します。
大野氏「先ほど平良の方から、アプリの利用促進のため、顧客にメリットのあるクーポン施策といった協力体制を整えていった話をしましたが、それに加えて月次単位でアプリダウンロード数の目標を立て、店舗別、ブロック別で実績の進捗を追っていて、上位店には成功事例や失敗事例を共有してもらっています。インセンティブというほど大きくは無いかもしれませんが、評価や賞与に反映しています」
清水氏「アーバンリサーチでは、アプリのダウンロード数は会員獲得の延長にあるものと考えて、会員獲得数に応じてスタッフにインセンティブをお渡しています。『アプリから会員登録していただくとこんなサービスがあります』というのをしっかり説明してもらうようにしていますね」
榎本氏は店舗との連携によってアプリのダウンロード数を増やしていっても、その後顧客のアプリ利用が促進されるとは限らないと話します。
榎本氏「お客様のデジタルリテラシーによっても、アプリを利用の促進が進んでいくかどうかは変わると思います。アプリは有効なOMOツールとして語られることが多いですが、自社のお客様が皆、ハードルを感じずに使っていただけるかというと、そうではない場合もあって『リアルなカードの方が良い』というお客様もいらっしゃる。
我々も昨年、店舗のお客様にECクーポンを配布したんですが、アプリでも配布できる中、紙のクーポンを配りました。店舗に来てくださっているお客様には、紙の方が親しみがあるだろうと考えたんです。そこから少しでもECを体験してもらい、少しずつ“デジタルの壁”を取り除いていく。まずは自社のお客様に向き合うことが大切だと思います 」
顧客の声を集め、改善の優先順位付けに活かす
パネルディスカッションでは、顧客の声を集め改善に活用する取り組みについてもお話しいただきました。アーバンリサーチとストライプインターナショナルでは、KARTEの「CX Survey」を実施。数多く集まった定性的なコメントをもとにアプリの改善に繋げていきました。
清水氏「以前からNPSを実施したいと考えていたので、KARTEのCX Surveyを実施することにしました。1ヶ月間限定で『アンケートにお答えいただけませんか』というポップアップを表示したところ、非常に多くのお客様に記入していただき、定性的なコメントまで書いていただいた数だけでも5000通以上の回答が集まりました」

CS Surveyのアンケートとレポートイメージ
清水氏「全てに目を通して、まとめていく中で『やっぱりここだよね』という改善点が見えてくるので、改修した部分について半年後に再びNPSで検証する予定にしています」
榎本氏「KARTEのCX Surveyはストライプインターナショナルでも実施しています。『画像表示が遅い』『重い』などの改善点に加えて、『安く購入できる』『商品発送までが早い』といった評価をいただくこともあります。自分たちでは気付きにくいことを知ることができますね。
また、実際に改修を進める時も『自分がこうしたい』ではなく『お客様からこういう声がたくさん上がっています』という方が社内も納得しやすいこともあります。 そういう面でも第三者的なデータには意味があると感じます」
大野氏「ライトオンでもお客様の声を拾っていく中で『遅い』や『重い』などのスピードの改善や、検索機能の強化に関するものが多かったので、アプリリニューアルの第2段階として、優先的に取り組むようにしています」
3社とも共通して、顧客の声を起点にアプリの改善を続けています。こうしたNPSやCX Surveyは決して単発で終わるものではなく継続していくべきもの。顧客の声に向き合い続ける姿勢こそが重要だと清水氏は話します。
清水氏「NPSはもちろん、アプリであればアプリストアにレビューもいただいています。ときには辛辣なコメントもありますが、そこに向き合って解決していく方向でチームを運営していくこと。お客様の声を聞き続けることが重要ですね。
現在は様々なツールでアプリをダウンロードしてくださったお客様からの声を知ることができると思います。お客様からデータをいただいているので、その分より良い体験をお返ししていきたいですね」
次回のAPPDIVE#5でも大手アパレルEC2社が登壇
次回のAPP DIVEも「しくじり」をテーマに、株式会社オンワードデジタルラボと株式会社TSIのアパレル2社に登壇いただきます。
ご興味のある方やお申込みされたい方は、下記より詳細をご確認ください。
https://plaid-jp.zoom.us/webinar/register/WN_rIomHeFmRd21qDArfnBhyA