KARTE STAR 2025 「GOLD STAR」受賞2社のKARTE活用術に迫る!| KARTE Friends Meetup vol.37レポート
2025年4月、「KARTE STARにいろいろ聞いてみよう!〜GOLD STAR受賞企業 JTBさん・野原グループさん篇〜」をテーマに、KARTE Friends Meetup vol.37を開催。イベントの中心となった両社によるパネルディスカッションの内容を中心にお届けします。
2025年4月、「KARTE STARにいろいろ聞いてみよう!〜GOLD STAR受賞企業 JTBさん・野原グループさん篇〜」をテーマに、KARTE Friends Meetup vol.37を開催しました。
当日は、KARTE STAR 2025で「GOLD STAR」を受賞された株式会社JTBと野原グループ株式会社の皆様をお招きし、普段KARTEをどのように活用しているのかについて、さまざまな質問をぶつけてみました!
イベントには、野原グループ株式会社 オンラインストアカンパニー マーケティング課より長井 文平さんと澤中 志寿子さん、株式会社JTB ホームページ戦略部 UI/UX課より湯本 和人さん、小野 道隆さん、佐藤 すな緒さんに「GOLD STAR」受賞記念の法被を着用してご登壇いただきました。
2社のGOLD STAR受賞インタビューでは、それぞれの企業でのKARTEを使った取り組み内容をご紹介しています。このレポートでは、イベントの中心となった両社によるパネルディスカッションの内容を中心にお届けします。
KARTE STAR 2025 「GOLD STAR」受賞インタビュー:株式会社JTB
KARTE STAR 2025 「GOLD STAR」受賞インタビュー:野原グループ株式会社
KARTEを活用した施策の管理や評価はどうしている?
イベント当日は、事前に寄せられた数々の質問に登壇者のみなさんが回答していく形で、KARTE活用における実践的なノウハウが共有されました。それぞれ、テーマごとにパネルディスカッションの内容を紹介していきます。

月あたりの施策数と評価期間は?
野原グループでは、現在約250個の施策を実施しており、月に10件程度の新たな施策を投入しています。長井さんによれば「画面のキーワードに対して接客を出すというシンプルな施策が多いですが、セールなどの期間中は増えることもあります」とのこと。施策の評価期間については、早いもので1〜2週間、一般的には1ヶ月程度で判断することが多いそうです。
JTBでは施策を「インフラ系案件」「A/Bテスト」「キャンペーン」の3つに分類。湯本さんによれば、インフラ系は多い時で月20件、A/Bテストは月1〜2回、キャンペーン系は月5〜6件ほど実施しているとのこと。A/Bテストは基本2週間の期間で実施し、施策を評価するのにボリュームが足りない場合はさらに2週間延長することもあるそうです。
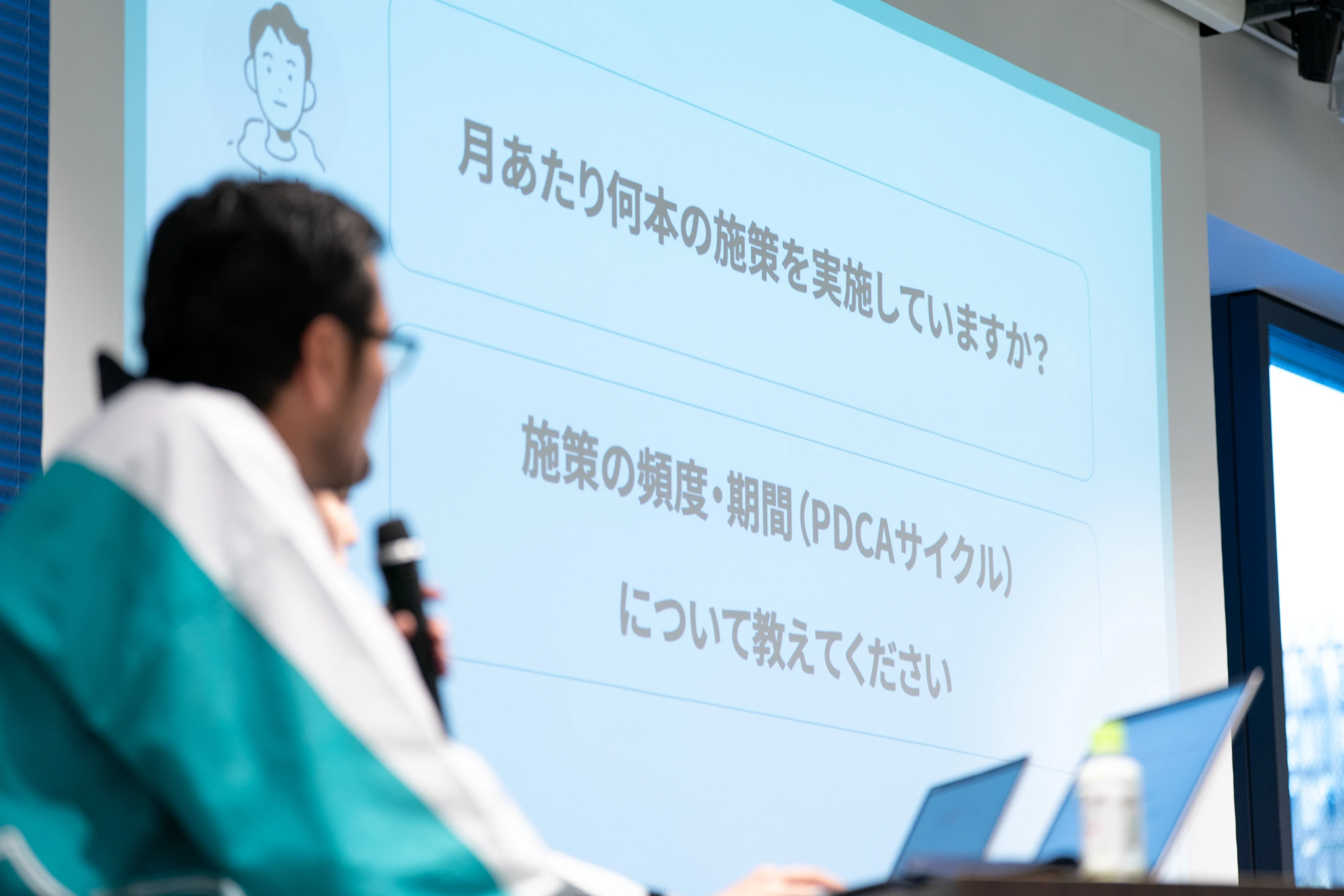
効率的な施策管理の工夫は?
野原グループでは、「課題ツリー」という仕組みを活用していると長井さんは説明します。課題ツリーはExcelで管理し、この中でKPIを設定して各施策がどのKPIに影響するかを把握しているとのこと。
「課題ツリーは、課題に対して施策案を紐づけるツリー構造で、各部署が作成し、すべてがつながっています。課題からロジカルに落とし込んでいくと、やるべきことが明確になり、インパクトの大きい施策から実施していきます」と、長井さん。

野原グループ株式会社 オンラインストアカンパニー マーケティング課 長井 文平氏
JTBでは、都度発生するインフラ系案件の要望をExcelで管理し、「どの画面で何をしたいか、対応希望日など」を記録。プロダクトマネージャーからの要望を受けて担当者を割り振る体制を取っているそうです。
湯本さんは「実装面ではエンジニアだけでなく、ノーコードで特定要素を変更するなどのテンプレート化も進め、年々ノーコードでできる範囲を広げています」と語り、A/Bテストについては、プロダクト課題のバックログからプロダクトマネージャーと相談する週30分の会議と、実際の実装に関する1時間の会議で運用していると説明しました。
効果測定に利用しているKARTEの機能は何ですか?
野原グループにおける効果測定について、長井さんは「基本的には接客の表示数、クリック率、ゴール達成率といった指標を見ています。アクション画面のデータをキャプチャして報告しています」と語ります。
JTBでの取り組みについて小野さんは「効果を測定する上で、Google Analytics 4(以下、GA4)との連携もしています。KARTEで取得したイベントデータをGA4のデータレイヤー変数にセットし、GA4側でも評価しています」と語りました。より精度の高い分析結果を求められる場合には、KARTE Datahubのクエリ機能を使ってBigQueryのローデータを抽出し、データを加工しながら分析を行うこともあるとのこと。
組織内でKARTE活用を波及させるには?
両社はKARTEの活用を担当部署以外にも広げているという点で共通しています。組織内にKARTEの活用を波及させる上で、それぞれどのような取り組みを行っているのかについても、質問が寄せられていました。
社内報告の方法は?
野原グループでは関連部署が集まって報告会を開催し、先ほどの課題ツリーのシートに沿って報告しているといいます。長井さんは「シートだけでは粒度が粗いので、Microsoft Loopを使って、『目的』『結果』『次の施策』などを簡潔にまとめています」と説明しました。

株式会社JTB ホームページ戦略部 UI/UX課 小野 道隆氏
JTBでは特にA/Bテストに関しては定例の共有会議を開催し、プロダクトマネージャーとの調整会議も設けているそうです。小野さんによれば「A/Bテストの進捗管理はJiraで行っています。Jiraを活用するメリットは、進捗管理や共有がしやすいだけでなく、コンフルエンスで作成している運用マニュアルとの連携がしやすいためです。」とのこと。
社内の他チームへのKARTE活用の拡大状況は?
KARTEの社内展開について、野原グループの澤中さんは「想像していた以上にスムーズに広がりました」と振り返ります。その背景について「KARTEでしか見られないデータがあったので、それをMD(マーチャンダイジング)やカスタマーサポートなど他部署に見せていくうちに『自分も使いたい』という声が自然に増えていきました」と説明しました。

野原グループ株式会社 オンラインストアカンパニー マーケティング課 澤中 志寿子氏
JTBでも2022年頃から他チームでの活用が始まったと湯本さんはいいます。「小野をはじめ、KARTEを活用しているメンバーが社外イベントなどで登壇する機会が増え、社内でも『キラキラしている』と注目され始めました。『私もやりたい』という声が広まり、技術的な面でも成功事例が増えていきました」と述べます。
社内の他部署で特に相性の良いところはどこか、と尋ねられた野原グループの長井さんは「うちはカスタマーサポートとの相性が良いですね。問い合わせがあったときに、接客で解消できる情報を出せると解決が早いです」と回答しました。

株式会社JTB ホームページ戦略部 UI/UX課 湯本 和人氏
JTBの湯本さんも長井さんが言及したカスタマーサポートとの相性について「RightSupportを使い始めて、お問い合わせ前の行動が可視化されるようになりました」と重ねます。加えて、「CRMチームもメルマガを配信した顧客のトラッキングにKARTEを使い始めていて、SEOチームもLPに流入した後のLPOとしてKARTEを使っています」と、さまざまな部署での活用が広がっていることに触れました。
組織への波及効果は?

株式会社JTB ホームページ戦略部 UI/UX課 佐藤 すな緒氏
JTBの佐藤さんは「デザイナーとして、入社時から課題発見のためにKARTE Liveを活用していました。またKARTEによって試行錯誤できる土壌があり、早くから様々なデザインをお客様に届けられたことで、多くの学びがあったと感じています。社内で相談されることも増え、社内でKARTEの有用性が認識されるようになっただけでなく、チームとしてのプレゼンス向上につながっていると感じます」と、若手社員の視点からのKARTEの広がりについて感じていることを語りました。
野原グループの長井さんも「社内の他部署からもKARTEの活用について声がかかるようになり、今後さらに活用の輪が広がっていくと考えられます」と、組織全体へとKARTEが広がることへの期待を寄せていました。
パネルディスカッション全体を通して、KARTE GOLD STARを受賞した2社の事例から、CX向上に向けた具体的な取り組みを学ぶことができました。
フェーズごとにKARTE活用をサポートするコンテンツ群を紹介
イベントの後半では、プレイドのカスタマーマーケティングチームの渥美 嘉月から、KARTEの活用をサポートするさまざまなコンテンツ群が紹介されました。

- サポートサイト:基本的な操作方法や設定を調べられる
- チャットサポート:サポートサイトでわからないことがある場合に問い合わせる
- KARTE Academy:体系的にKARTEを学ぶための講座を用意
- シナリオストア:施策のアイデアや実装イメージを得られる
- スキルアップ講座:KARTE Academyで施策の評価や改善の考え方など、次のステップに向けて必要なことを学べる講座
- 音声番組:移動時間などに気軽に学べるコンテンツ
これらのコンテンツは、「KARTE導入前」「KARTE活用中」「KARTE活用後」といったフェーズ別に、KARTE Friendsの皆様が何かつまづいた際に活用できるよう設計しています。
当日、イベントの参加者には、PDCAサイクルに合わせてアクションを書き込めるワークシートと、KARTE Academyの講座を一枚でまとめた「アカデミーマップ」を配布させていただきました。アカデミーマップに記載された二次元コードを読み取ると、Miroで作成したデジタルのアカデミーマップにアクセスでき、気になった講座に直接アクセスできるという仕組みです。

KARTE Friendsのみなさまをサポートするためのコンテンツ群のご紹介をした後、KARTE Academyを紹介する映像も上映しました。
「これからもKARTEの活用にお役立ていただけるようなコンテンツをつくっていきたいと考えています。もし、何かこうしたコンテンツを活用していて不明な点などあれば、いつでもご質問ください」と渥美はイベントの参加者に呼びかけ、紹介を終えました。
交流会を通じて業界をまたいで深まるつながり
イベントの締めくくりとして集合写真を撮影した後は参加者同士の交流会を開催。銀座のサンドイッチ専門店から手配されたパーティーサンドイッチとドリンクを楽しみながら、参加者同士やプレイドのメンバーとカジュアルに交流する様子が見られました。



今回、登壇いただいた野原グループとJTBも、それぞれ異なる業界に属する企業です。異なる業界であったとしても、KARTEの活用に関して互いに学べることはきっとあるはず。そう信じて、今後もKARTE Friends同士が交流する機会を作り出していきます。
次回のKARTE Friends Meetupにもぜひご期待ください。KARTEを活用した取り組みについて情報交換したい方、CXに関心のある方は、ぜひご参加ください!